
 |
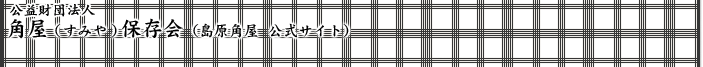 |
当館は新型コロナウイルスおよびインフルエンザ等感染症の予防と文化財保護に努めながら公開を行っております。多くの方に安心してご見学いただけるよう、人数制限および案内時間の設定にご理解とご協力いただけますようお願い申し上げます。 令和7年3月17日 角屋もてなしの文化美術館     
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【燭台】 |
|||
1 真鍮製燭台(松の間用) |
江戸後期 |
一基 |
|
2 鎌倉彫燭台(緞子の間用) |
江戸中期 |
一基 |
|
3 菊台座燭台(翠簾の間用) |
江戸中期 |
一基 |
|
4 扇台座燭台(扇の間用) |
江戸中期 |
一基 |
|
5 三脚形燭台(青貝の間用) |
江戸中期 |
一基 |
|
6 染付山水風景文燭台 |
江戸後期 |
一基 |
|
7 黒漆塗鐘形燭台 |
江戸後期 |
一基 |
|
8 三つ脚燭台 中川浄益作 |
江戸後期 |
一基 |
|
9 三つ脚燭台 中川浄益作 |
江戸後期 |
一基 |
|
10 秋草文燭台 |
江戸中期 |
一基 |
|
11 菊形燭台 |
江戸後期 |
一基 |
|
12 花亀甲紋手燭 |
江戸中期 |
一基 |
|
13 手燭 |
江戸後期 |
一基 |
|
14 円形雪洞手燭 |
江戸後期 |
一基 |
|
15 龕灯(がんどう) |
江戸末期 |
一基 |
|
16 網枠提灯 |
江戸後期 |
一基 |
|
【行灯・吊燈籠】 |
|||
17 黒漆塗灯架 |
江戸後期 |
一基 |
|
18 朱塗六⻆形行灯 |
江戸後期 |
一基 |
|
19 手提木地行灯 |
江戸後期 |
一基 |
|
20 待合行灯 |
江戸後期 |
一基 |
|
21 吊燈籠 |
|
一基 |
|
22 六角吊燈籠 |
|
一基 |
|
【明かり障子】 |
|||
23 腰高重舞良障子(旧松の間) |
|
一面 |
|
24 吹き寄せ組子障子(緞子の間) |
|
一面 |
|
25 桧垣の間障子(桧垣の間) |
|
一面 |
|
26 衽組入子菱組障子(八景の間・非公開) |
|
四面 |
|
27 籠目組子欄間障子(梅の間・非公開) |
|
二面 |
|
【もてなしの器】 |
|||
28 吉野漆絵膳椀揃 |
|
一式(一期) |
|
29 鳳凰蒔絵膳椀揃 |
一式(二期) |
||
【絵画】 |
|||
30 「⻆屋の窓図」 |
三輪晃勢筆 |
一幅(一期) |
|
31 「太夫かしの式図」 |
松田俊筆 |
一幅(二期) |
|
【参考資料】 |
|||
32 扇形・団扇型・隅丸矩形・ |
|
一面 |
|
*【絵画】・【もてなしの器】のみ資料・作品保護のため、下記日程で展示替えを行います。
- 一期 9月14日(日)〜10月26日(日)
- 二期 10月30日(木)〜12月14日(日)